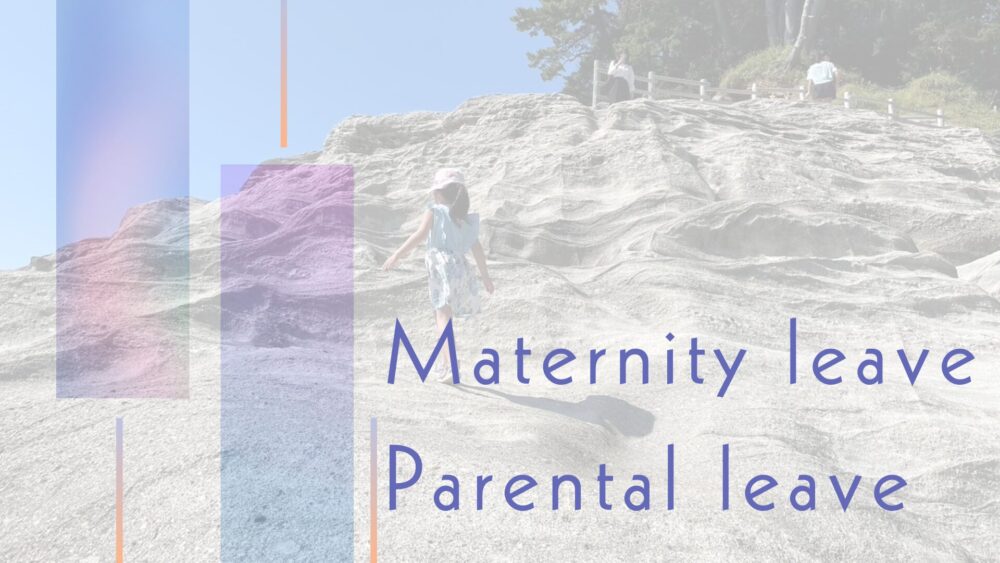広告

「育休中の収入が減る分、もらえるお金はきちんと受け取りたい。」
そう思って調べてみたものの、制度ごとに申請先や期限が違っていて、何から手をつければよいのか分からない…
そんな不安を抱えていませんか?
出産・育児の制度を正しく使えば総額200万円にもなると言われていますが、タイミングや申請手順を間違えると大きな損失につながります。
例えば、「児童手当の申請が出生から15日を過ぎて1ヶ月分を受け取れなかった」「帝王切開で高額療養費制度を知らず30万円を全額自己負担した」など、知識不足による失敗は珍しくありません。
私は現在、3人の子どもを育てながら働く現役銀行員で、FPとしてママたちの家計相談も行っています。

第一子のときは失敗もありましたが、第三子では申請漏れなく約300万円の給付を受け、育休中も安心して子育てに専念できました。
この記事では2025年最新の出産育児制度15選を解説し、わたし自身の体験談をもとにFPとしてアドバイスいたします。

末尾では「申請期限が一目でわかるチェックシート」と「給付金計算ツール」をLINE限定で無料プレゼントしています。
ツールを活用すれば、「手続き漏れ」を防ぎ、自身が受け取れる「給付総額」を把握できるため、出産前後の不安を大幅に軽減できるでしょう。
限られた時間でも効率よく出産準備を進め、安心して出産に臨んでくださいね。
出産前後に申請すべき15の制度と手続き一覧(申請先・金額・期限まとめ)
| 申請先 | 制度名 | 金額の目安 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| 会社・健保組合 | ①産前産後休業届 | – | 出産後8週まで |
| 会社・健保組合 | ②育児休業申請書 | – | 育休開始前 |
| 会社・健保組合 | ③健康保険加入(扶養) | – | 出生届提出後すぐ |
| 会社・健保組合 | ④出産育児一時金 | 50万円 | 出産後速やかに |
| 会社・健保組合 | ⑤出産手当金 | 給与の2/3×98日 | 産後56日経過後すぐ |
| 会社・健保組合 | ⑥育児休業給付金 | 給与の50〜67% | 育休開始後4ヶ月後の月末まで |
| 会社・健保組合 | ⑦会社の扶養手当 | 会社規定による | 出生後会社規定による |
| 会社・健保組合 | ⑧出生後休業支援給付金 | 給与日額13%×14日 | 休業終了後2ヶ月以内 |
| 市区町村 | ⑨出生届 | – | 出生後14日以内 |
| 市区町村 | ⑩児童手当申請 | 月1〜1.5万円 | 出生後15日以内 |
| 市区町村 | ⑪乳幼児医療費助成申請 | 医療費ほぼ無料 | 出生後できるだけ早く |
| 市区町村 | ⑫出産・子育て応援給付金 | 計10万円 | 自治体案内に従う |
| 税務署・その他 | ⑬医療費控除 | 税金還付 | 出産年の翌年2月〜3月 |
| 税務署・その他 | ⑭高額療養費制度申請 | 自己負担上限設定 | 支払後2年以内 |
| 税務署・その他 | ⑮医療保険金申請 | 入院・手術給付金 | 出産・入院後 保険会社規定による |
申請先別に一つずつ丁寧に解説していきますね。
市区町村役所での手続き
市区町村役所でおこなう手続きは以下です。
- 出生届
- 児童手当
- 乳幼児医療費助成
- 出産・子育て応援給付金

申請期限が短いモノが多いので、注意が必要です。
① 出生届|戸籍登録のため14日以内に提出が必要
出生届は赤ちゃんが法的に存在する人として認められるための重要な手続きです。
- 申請先:市区町村役所
- 必要書類:出生届書、本人確認書類、母子手帳
- 期限:出生日を1日目として14日以内
- ポイント:自治体によってはオンライン申請可能
体験談とワンポイントアドバイス
注意点は期限が「出生日を1日目として14日以内」という点。
わが家は2人目の名前がなかなか決まらずギリギリまで悩み、出生日を1日目にカウントせず1日遅れて提出。

幸い罰金等は特に言われませんでしたが、大幅に遅れると罰金が科せられる場合もあるようです。
さらに、出生届が遅れると他の手続きも進められません。
健康保険証の発行が遅れて医療費が一時全額自己負担になったり、児童手当の支給開始が遅れたりなど影響が大きいため、出生届はできるだけ早く提出しましょう。

出生届提出時に、同じ役所で児童手当とマイナンバーカードも同時に申請することもできます。
できるだけまとめられる手続きは一気に行い、何度も役所に足を運ぶ手間を省きましょう。
ご参考:法務局HP
② 児童手当|18歳まで最大約200万円(月1万〜1.5万円)
- 受給金額
- 3歳未満:月15,000円
3歳〜小学生:月10,000円(第3子以降15,000円)
中学生・高校生:月10,000円期限:出生日から15日以内
- 申請先:市区町村役所
- 必要書類:印鑑(認印可)・申請者の健康保険証・申請者名義の通帳・申請者&配偶者のマイナンバー
体験談とワンポイントアドバイス
児童手当は出産・育児関連の給付の中でも重要な制度の一つで、18歳まで継続して受け取るとトータル200万円にもなります。

申請が1日でも遅れると1ヶ月分損してしまうため、出生届と同時に申請しておきましょう。
わが家は1人目の出産前に夫の名前で児童手当専用の口座を開設しました。生活費と混ざることなく子どもの教育費ためのお金として貯蓄や投資に回せるため、本当にやってよかったです。
ご参考:子ども家庭庁HP
③乳幼児医療費助成|子どもの医療費がほぼ無料
- 内容:医療費の窓口負担が無料or数百円程度になる
- 対象年齢:自治体により異なる(就学前〜18歳まで)
- 申請:健康保険証取得後すぐ
体験談とワンポイントアドバイス
この制度は自治体によって内容が異なります。私が住んでいる地域では中学生まで医療費無料ですが、東京都では18歳まで無料。引っ越しを検討している方は、このような子育て支援制度も比較材料に入れるといいですよ。
注意点は、医療証が発行される前に受診した場合です。この場合は一度医療費を支払うことになりますので、領収書は必ず保管しておいて、医療証が手元に届いたら払い戻し申請をしましょう。
わが家の場合は産後、子どもの入院が長引き、保険証もできていなかったため本来は医療費を支払う必要がありました。しかし、この産院は1ヶ月健診時に保険証と医療証を持ってくれば良いという条件で病院が立て替えてくれていました。(つまり手出しなしで済んだのです。)このように病院によって対応は違いますので、事前に確認しておくと安心です。
④出産・子育て応援給付金|計10万円支給(保健師面談付き)
2023年から本格的に始まった比較的新しい制度で、妊娠時5万円+出生時5万円が受け取れます。
- 内容:現金またはクーポンで受給(自治体による)
- 特徴:保健師面談とセット
- 申請:妊娠届・出生届提出後の面談時
体験談とワンポイントアドバイス
私の出産時代にはなかった制度のため体験談は語れませんが、保健師さんとの面談がセットになっているのが特徴です。
特に初めての子は右も左もわからず、発達具合や症状など些細なことが気になってしまうもの。この時期に専門家とのつながりが持てることはとても心強いことです。

申請方法は自治体により異なるので、よく確認してくださいね。
会社・健康保険組合での手続き
会社・健康保険組合でおこなう手続きは以下です。
- 産前産後休業届
- 育児休業申請書
- 健康保険加入(扶養手続き)
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金(2025年新設)
- 会社の扶養手当(家族手当)

効果が大きいモノがたくさんあるため、おさえておきましょう!
①産前産後休業届|産休取得のための正式手続き
- 対象要件:雇用保険加入者(会社員・公務員)であること
- 期間:産前6週間・産後8週間
- 申請期限:出産後8週まで
- 必要書類:産前産後休業届、医師の診断書
体験談とワンポイントアドバイス
産前産後休業は労働基準法で定められた権利です。

産前6週間は本人の希望により取得できますが、産後8週間は必ず取得しなければなりません。
会社によっては独自の産休制度があることもあるので、事前に確認しておきましょう。
また、スムーズな業務引継ぎのためにも早めに上司に報告することをおすすめします。
私は妊娠が分かって比較的すぐの妊娠7~8週目位には報告していました。
② 育児休業申請書|育休取得のための事前申請
- 対象要件:雇用保険加入者(会社員・公務員)であること
- 期間:原則1歳まで(条件により2歳まで延長可能)
- 申請期限:育休開始日の1ヶ月前まで
- 必要書類:育児休業申請書、出生証明書等
体験談とワンポイントアドバイス
育児休業は男女問わず取得できる制度です。

2025年4月からは夫婦で育休を取得する場合の給付が手厚くなるため、パートナーと相談して計画的に取得することをおすすめします。
③健康保険加入(扶養手続き)|赤ちゃんの保険証取得
- 申請期限:出生届提出後できるだけ早く
- 必要書類:健康保険被扶養者届、出生証明書
体験談とワンポイントアドバイス
健康保険証は1ヶ月健診までに必ず必要になります。

発行までに2〜3週間かかることもあるので、出生届を提出したらすぐに手続きを始めましょう。
間に合わない場合は1ヶ月検診の費用を支払い、後日領収書を持って病院に払い戻し申請に行く必要があります。
わたし自身間に合わなかったことがありますが、生まれたばかりの赤ちゃんを連れての病院は一苦労です。二度手間にならぬよう、早めの手続きをおすすめします。

基本的には年収が高い方の健康保険に入るのが原則ですが、夫婦の年収差が1割以内なら、どちらの扶養に入れても問題ありません。
勤務先の健康保険組合の付加給付や家族手当などを比較して有利な方を選びましょう。
④ 出産育児一時金|出産費用に充てられる50万円の給付
- 金額:原則50万円(赤ちゃん1人につき)
- 方法:直接支払制度が便利(事前に産院で手続きが必要)
- 対象:妊娠4ヶ月(85日)以上の出産
- 期限:出産翌日から2年以内
体験談とワンポイントアドバイス
出産費用に一時金を直接充当する「直接支払制度」という制度があります。
高額な現金を事前に準備する必要がなく、実際の出産費用との差額のみを支払えばOKというモノ。
ほとんどの産院で利用可能です。
例えば出産費用が48万円だった場合、一時金50万円から48万円が産院に直接支払われ、差額の2万円があなたに支給されます。逆に出産費用が52万円だった場合は、差額の2万円を窓口で支払います。

わたしは1人目2人目の出産時に直接支払制度を利用しました。
出産前後のバタバタした時期に大金を用意する必要がないのは、精神的にも楽でした。

3人目の時はあえて直接支払制度を使わず、事後申請を行いました。
クレカ払いのできる産院だったため、クレジットカードで出産費用約70万円を支払い、入会特典の大量ポイントをゲット。(マイルに換えてハワイ旅行に使いました)
どうせ支払うお金なので、現金に余裕のある方はこのような使い方もおすすめです。
ご参考:厚生労働省HP
⑤出産手当金|給与の2/3を最大98日間支給
出産手当金は産休中の生活費を補償してくれる制度です。給与の約2/3がもらえるので、収入がゼロになる心配はありません。
- 対象:会社員・公務員(健康保険加入者)
- 金額:給与日額の2/3×最大98日間
- 期間:産前42日+産後56日
- 特徴:非課税所得
- 申請:会社が代行することが多い
体験談とワンポイントアドバイス
出産手当金は非課税なので、所得税や住民税がかからないのも嬉しいポイントです。
月給25万円の場合の計算例↓↓
- 日額=25万円÷30日=約8,333円
- 出産手当金日額=8,333円×2/3=約5,555円
- 98日間の合計:約54万円

わたしの場合は、産休期間中も会社から給料が支払われていたためこの手当は出ませんでした。
会社の制度も事前に確認しておきましょう。
ご参考:厚生労働省HP
⑥育児休業給付金|最長2年・給与の最大67%支給
- 受給金額
- 開始〜180日:給与の67%
181日以降:給与の50%
- 期間:最長2歳まで
- 2025年改正:夫婦で育休取得時は一定期間80%(手取りの100%)に!
- 特徴:非課税所得
体験談とワンポイントアドバイス

育児休業給付金は仕組みをあらかじめ理解していれば、手取りを増やす工夫が可能になります。
そのためには早めの対策が大切です。
- 月給25万円で1年間育休を取得した場合の試算
- 最初の6ヶ月:25万円×67%×6ヶ月=約100万円
後の6ヶ月:25万円×50%×6ヶ月=約75万円
合計:約175万円
非課税所得なので、手取りで考えると現役時代の約8割の収入を確保できる計算になります。
ご参考:厚生労働省HP
⑦出生後休業支援給付金(2025年新設)|最大28日間給与の手取り同等分を受給可能
この新制度は、男性の育休取得促進を目的とした画期的な制度です。
夫婦で協力して育休を取得することで、経済的な不安を大幅に軽減できます。
- 条件:夫婦で生後8週間以内に計14日以上育休取得
- 金額:給与日額の13%相当×14日間
- 効果:育児休業給付金と合わせて手取り実質10割相当も
- 注意点:給付金額の上限あり
体験談とワンポイントアドバイス
2025年に新設された制度のため、私自身は経験がありません。
しかし、産後の大切な時期に男性が育休を取得する意義は大きいと思いますので、ぜひパートナーと相談して活用を検討してみてください。

この制度は男性の育休の取り方が手取り金額を左右するポイント。
ご参考:厚生労働省HP
⑧会社の扶養手当(家族手当)|勤務先により毎月支給される手当制度
扶養手当は約7割の企業で採用されていますが、全ての会社にあるわけではありません。
特に中小企業では制度がない場合も多いので、まずは夫婦それぞれ勤務先の制度を確認することが大切です。
- 対象: 会社員・公務員(勤務先に扶養手当制度がある場合)
- 金額: 月額5,000円〜20,000円程度(会社により大きく異なる)
- 期間: 扶養認定期間中(一般的には18歳または22歳まで)
- 申請期限: 出生後会社規定による(多くは1ヶ月以内)
- 必要書類: 扶養手当申請書、出生証明書、健康保険証のコピー等
体験談とワンポイントアドバイス
わが家の場合、ありがたいことに夫の会社に扶養手当の制度があり、子ども一人につき12,000円ずつ受給中。
こちらも遡って受給はできないため、出産後すぐに申請しないと損してしまいます。

扶養手当は給与所得として課税対象です。
児童手当とは異なり、所得税・住民税がかかる点にご注意ください。

夫婦共働きの場合、どちらの勤務先で扶養手当を申請するか選択できます。
金額を比較して、より有利な方で申請しましょう。
税務署・その他での手続き
税務署などでおこなう手続きは以下です。
- 医療費控除
- 高額療養費制度
- 医療保険金申請

医療費が高額になった場合の対応方法です。ご自身が対象なら検討してください。
① 医療費控除|出産費用や妊婦健診で税金が戻る制度
- 条件:年間医療費10万円超(所得200万円未満の場合は所得の5%)
- 対象:妊婦健診、出産費用、子どもの医療費、通院交通費
- 期限:翌年2/16〜3/15(還付申告は5年間遡及可)
- 方法:オンライン申請(e-Tax)がおすすめ
体験談とワンポイントアドバイス
出産した年は医療費が高額になりがちなので、医療費控除の対象になる可能性が高いです。

わたしも出産の年は毎回申請しています。治療費、薬代、交通費も領収書を残しておきましょう。
- 対象となる医療費の例
- 不妊治療費用
妊婦健診費用(補助額を差し引いた自己負担分)
出産費用(出産育児一時金を差し引いた自己負担分)
妊娠中・産後の治療費
通院のための交通費(公共交通機関)
産後の母体回復のための治療費
私の第一子出産時は、妊婦健診から出産、産後の治療まで含めて年間30万円ほどの医療費がかかり、医療費控除で約4万円の還付を受けることができました。
ご参考:国税局HP
②高額療養費制度|帝王切開など高額医療に備える自己負担上限制度
帝王切開や切迫早産での入院など、予想外に医療費が高額になった場合に活用できる制度です。

たとえば年収約370万円~770万円の場合、月の医療費がいくらかかろうが負担限度額は8万円台になります。
- 内容:月の医療費自己負担上限を設定
- 事前準備:「限度額適用認定証」取得で窓口負担軽減
- 申請期限:医療費支払い月の翌月から2年以内
- ポイント:保険診療分のみ対象
体験談とワンポイントアドバイス
「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払いを自己負担上限額(年収約370万円~770万円の場合は8万円台)までに抑えることができます。

また加入している健康保険によっては「付加給付制度」というモノがあります。(大手企業に多いです)
高額療養費に上乗せして医療費を払い戻してくれるため、さらに自己負担金額は低くなります。(健康保険組合によりますが、月の限度額が25,000円程度になるモノもあります)
ご参考:厚生労働省HP
③医療保険金申請|民間保険の入院・手術給付金
民間の医療保険から保険金を請求する内容です。
- 対象:帝王切開等の異常分娩
- 内容:入院給付金、手術給付金など
- 要件:妊娠判明前の加入が原則
- 申請:速やかに(一般的に3年以内)
体験談とワンポイントアドバイス
民間の医療保険は、公的医療保険でカバーしきれない部分を補う役割があります。
特に、妊娠が判明する前に医療保険に加入しておくことが、保障を得るための重要なポイント。

妊娠判明後は、出産に関する特約を付加できなかったり、加入自体が難しくなったりするケースが多いからです。
民間の医療保険に加入している場合、帝王切開などの異常分娩が給付対象になることがあります。
吸引分娩や鉗子分娩でも保険金が支払われる場合もありますので、保険加入中の方は必ず確認しましょう。
制度を活用するとどれくらいもらえる?金額シミュレーション
公的な制度だけを実際にすべて受給するとどれくらいもらえるのか、具体例で見てみましょう。

以下のシミュレーションは、「夫婦共働き、月給25万円」という方をモデルに計算しています。
| 制度 | 金額 |
| 出産育児一時金 | 50万円 |
| 児童手当(18年間) | 約200万円 |
| 出産手当金 | 約16万円 |
| 育児休業給付金(1年) | 約150万円 |
| 医療費控除 | 数万円 |
| 合計 | 約420万円+α |
これはあくまでも一例ですが、しっかりと制度を活用すればこのように数百万円の支援を受けることができます。
【私のリアル体験談】よくある疑問と対処法
ここでは、私が実際に3人の出産・育児を経験した中で直面したことや、ファイナンシャルプランナー(FP)として多くのママたちの相談を受けた中でよく聞かれる疑問とその対処法をより具体的にご紹介します。
Q1: 里帰り出産の場合、手続きはどこでするの?
A1: 基本的に、赤ちゃんの出生届以外のほとんどの手続きは、親(主に赤ちゃんを扶養に入れる方)の住民票がある自治体で行います。
- 出生届
- 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の役所に提出。
赤ちゃんが生まれた場所の市区町村役場でも提出できます。(里帰り先の役場に提出後、住民票のある自治体へ情報が伝達される)
- 児童手当、乳幼児医療費助成、出産・子育て応援給付金など
- 住民票のある自治体(=普段住んでいる場所の自治体)への申請が必要。
体験談とワンポイントアドバイス
里帰り出産を予定している場合は、出産前に夫婦で「誰が、どの手続きを、いつまでに、どこに提出するか」を具体的に話し合い、必要書類をまとめておきましょう。

特に出生届以外の役所での手続きは、里帰り期間中に住民票を移さない限り、元の住民票のある自治体で行う必要があるため、協力が必要です。
Q2: 夫の会社にも何か手続きが必要?共働き夫婦の場合の注意点
A2: 共働き夫婦の場合は、夫婦それぞれの勤務先で手続きが発生するため、漏れがないよう注意が必要です。
- 配偶者控除・扶養控除の変更
- 赤ちゃんを夫の扶養に入れる場合、年末調整や確定申告で「扶養親族等申告書」などを提出し、扶養家族が増えたことを会社に申告します。
妻も年収が123万円以下になる場合は夫の扶養に入りましょう。(夫の所得税や住民税が軽減されます)
- 健康保険証の交付
- 赤ちゃんを夫の健康保険の扶養に入れる場合、夫の勤務先を通じて健康保険組合または協会けんぽに申請します。
- 育児休業の取得(育児休業給付金、出生後休業支援給付金)
- 夫も育児休業を取得する場合、育児休業給付金の申請や、2025年新設の出生後休業支援給付金の申請など、夫の勤務先での手続きが必要になります。
特に「産後パパ育休(出生時育児休業)」の取得を検討している場合は、会社への早めの連絡が必須です。
- 会社の扶養手当
- 出産祝い金や家族手当などの慶弔見舞金制度がないか、忘れずに確認しましょう。
Q3: 申請を忘れて期限を過ぎてしまったらどうなる?対処法は?
A3: 制度によって対応は異なりますが、「もう間に合わない」と諦める前に、まずは各担当部署にすぐに問い合わせることが重要です。
- 児童手当
- 原則として、申請が遅れた月以降の手当は支給されますが、残念ながら遅れた月分の手当は支給されません。15日以内という期限を守りましょう。
- 出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金
- 時効が2年と定められていますが、原則として速やかな申請が求められます。
大幅に遅れると、過去の分が受け取れなくなる可能性があります。
- 出産育児一時金
- 申請期限は出産日の翌日から2年間と比較的猶予があります。
- 医療費控除
- 確定申告の期限を過ぎても、5年間は遡って申告できる場合があります(還付申告)。
- 医療保険金
- 保険会社によって時効が異なりますが、3年程度が一般的です。まずは保険会社に連絡しましょう。
体験談とワンポイントアドバイス
「気づいたらすぐに問い合わせる」ことが何よりも大切です。

各制度には時効が設けられているため、時間が経つほど受け取れる可能性が低くなります。
諦めずにまずは電話相談してみてくださいね。
Q4: 電子申請はできる?忙しい産後に役立つデジタル活用術
A5: 最近はマイナポータルを活用した電子申請が可能な手続きが増えています。産後は外出が難しい時期なので、積極的に活用することで手間と時間を大幅に削減できます。
マイナポータルでの電子申請対応手続き(一部):
- マイナポータルでの電子申請が可能な制度
- 児童手当の申請
出産育児一時金の申請(一部の健康保険組合)
健康保険証の交付申請(一部の健康保険組合)
国民年金保険料の免除申請
所得税の確定申告(e-Tax)
体験談とワンポイントアドバイス
確定申告はe-Taxを利用することで、自宅から簡単に手続きを終えることができました。
その他の手続きも随時オンライン申請できるものが増えているので、申請前に確認してみてください。
いちいち足を運ぶ必要がなくなり、グッと時短になります。
まとめ
出産・育児でもらえるお金や支援は「申請主義」であり、申請しなければ1円も受け取れません。
この記事とチェックリストを活用すれば、数百万円規模のサポートをしっかり受け取ることができます。
手続きは「早め・確実」が鉄則です。

迷ったときはこの記事を見返し、以下のポイントを意識して進めてください。
- 出生届・健康保険証・児童手当の3大手続きを最優先で進める
- その後も時系列でチェックリストを活用し、もれなく申請する
- 迷ったら役所・会社・保険会社にすぐ相談する
- 夫婦で事前に役割分担と情報共有をしておく
※制度は随時更新されるため、最新情報は各自治体や勤務先で必ずご確認ください。
ここまでご覧いただき、本当にありがとうございました。
出産・育児は、喜びもあれば、初めてのことで戸惑うこともたくさんありますよね。特に「お金」や「手続き」のことは、なかなか人に相談しづらいと感じる方もいるかもしれません。
私もたくさんの壁にぶつかりながら3度の産休・育休を乗り越えてきました。だからこそ出産や育児を頑張る方の力になりたいと思っています。

このブログが出産・育児ライフをより良いモノにしていただけるキッカケになると幸いです。
この他、日々の育児のヒントや、FPならではのお金に関する情報は、あかねのInstagramをフォローしてチェックしてください。
オリジナル便利ツールをプレゼント
あかねの公式LINE登録者限定で、以下をプレゼントしています↓↓
- 申請期限付き出産手続き「チェックリスト」
- 最新法改正対応の「給付金計算ツール」
- 受け取り方法
- あかねのLINE公式アカウントに登録後、メニューから「プレゼント希望」とメッセージを送ってください。
すぐにダウンロードリンクをお送りします。
①出産手続きチェックリスト

出産予定日を入力するだけで、各種手続きの申請期限や必要書類が自動で整理できるチェックリストです。
提出漏れ防止に活躍に役立ちます。

メモ欄には夫婦の役割分担を入力しておきましょう。
メモ欄には夫婦の役割分担を入力しておきましょう。
②育児休業給付金計算シート

2025年最新の育児休業給付金・出生後休業支援給付金に対応した給付金計算ツール。

医療費控除の概算、児童手当の金額も自動計算されます。
産休育休中の家計管理やライフプランニングにも活用できます。
これらは外出先や役所の窓口でもすぐに確認でき、印刷して冷蔵庫に貼ったり、スマホで持ち歩いたりと、出産・育児準備をサポートできるでしょう。
- 受け取り方法
- あかねのLINE公式アカウントに登録後、メニューから「プレゼント希望」とメッセージを送ってください。
すぐにダウンロードリンクをお送りします。

「もっと詳しく自分のケースについて相談したい」「チェックリストをスプレッドシート形式で欲しい」という方は、個別相談も承っています。
無料プレゼント多数